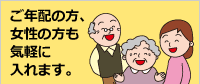眼精疲労


こんなお悩みはありませんか?

目が充血していることが多い
目に違和感を感じる
目の疲れからの頭痛がある
目が乾燥してショボショボする感じがある
イライラが募る
夜、寝れない
目の焦点を合わせるのがつらくなった
睡眠不足
長時間のパソコン作業
近視・遠視・乱視のいずれかが該当する
頭が重い感じがある
涙が出てしまう
視力低下
まぶたがピクピクと痙攣する
眼精疲労からくる、首・肩回りのハリ感・コリ
仕事の多忙・合間合間の休息が上手く取れていない
眼精疲労についてで知っておくべきこと

眼精疲労とは、視作業を行うことにより、眼痛・目のかすみ・まぶしさ・頭痛・充血などの目の症状が現れることを指します。さらに症状がひどくなると、吐き気や首・肩周りのコリ感、ハリ感といった全身的な症状が出ることもあります。休息や睡眠をとっても回復しない状態を指すことが多いです。
構造的な観点から説明すると、眼精疲労は、水晶体の厚さを変化させてピントを調節する毛様体筋の緊張が原因とされています。近くを見るときには、レンズとなる水晶体を厚くするために毛様体筋が緊張します。しかし、脚や腕の筋肉が長時間緊張していると疲れるのと同様に、毛様体筋も緊張状態が長く続くと疲れてしまいます。
症状の現れ方は?

症状としては、最初は軽度のものから始まり、「目が重い」「目がショボショボする」「目が疲れる」といった感覚が現れます。そこから進行し、目の充血や涙が出る、まぶしさを感じるといった段階的な症状が現れることが多いです。非常につらい場合、慢性化することで症状の軽減がなかなか進まないこともあります。
また、遠視・近視・乱視が関係していたり、眼痛や周囲が霞んで見える、物体とのピントが合いにくい、まぶたがピクピクと動く(これを痙攣と言います)といった症状も見られます。
さらに、自律神経の失調が原因となる場合もあります。交感神経と副交感神経のバランスが崩れることにより、寝つきが悪くなる、めまいや立ちくらみを感じる、ストレスをより強く感じることがあることもあります。
その他の原因は?

根本的な原因として多いものについてご紹介いたします。
まず、デスクワークやパソコン作業が多いといった一般的な原因をよく耳にしますが、「ドライアイ」という言葉を聞いたことはありますか?
ドライアイの症状には、「目が乾く」だけでなく、「目がかすむ」「まぶしい」「目が疲れる」「目が痛い」「目がゴロゴロする」「目が赤い」「涙が出る」「目ヤニが出る」といったさまざまな症状が含まれます。
ドライアイは加齢や生活環境の変化により引き起こされることが多い症状です。涙の量や質の低下、パソコンやスマホの長時間使用、エアコンなどの乾燥した環境が原因となることがあります。また、ドライアイは自己免疫疾患に関連する場合もあります。
眼精疲労を放置するとどうなる?

進行した状態についても触れさせていただきますと、頸部や肩の痛み、コリ感をよく聞きますが、これは自律神経と深く関連しています。自律神経とは、交感神経と副交感神経で構成されています。
交感神経は、目が覚めている時や仕事中、運動中など、何かに集中している時に優位になる神経です。
副交感神経は、夜間や睡眠時、リラックスしている時に優位になる神経で、内臓器官の調節や体温調節を行い、身体の機能のバランスを保っています。
頸部の凝りについては、筋肉が強く緊張した状態が続くことが原因となります。その中でも、後頭下筋群という場所が特にコリ感を感じやすい部分となります。
当院の施術方法について

整骨院では、病院ではないため臨床的な検査や診断などの医療行為は行うことができませんが、目の疲れや頭痛の軽減が期待できる施術をご提供しております。
まず、指圧を用いて、筋肉そのものの緊張をほぐし、リラックスさせる施術を行います。これは、一般的にマッサージとして知られています。
さらに、当院では「ドライヘッド矯正」という施術にも特化しています。眼球付近にある筋肉にアプローチし、頭部(側頭部、前頭部、頭頂部)の筋肉の緊張を緩和することを目指します。これにより、頭の重さやだるさ、首の可動域が広がることが期待できます。
また、副交感神経を優位にするため、遠赤外線を使用して体を温めた後に施術を行います。これにより、一回の施術で変化を感じやすくなります。
改善していく上でのポイント

まずは、ご自身のお身体がどのような状態にあるのかを知ることが重要です。
生活環境については、仕事の合間に休息を取れているか、スマホやパソコンの使用時間が長すぎないか、夜の寝つきやストレス、睡眠時間がしっかり確保できているかを確認することが大切です。
スマホについては、日常的に欠かせないものだとは思いますが、スマホ画面のフィルムをブルーライトカットのものにし、目の負担を減らすことができます。また、夜寝る際には目の周りを温めることで副交感神経を優位にし、リラックスした状態で寝ることができるでしょう。
これらの方法を試していくだけでも、目に見えるものではないかもしれませんが、負担が軽減される可能性が高いと考えます。それでも軽減が見られない場合は、医療機関での適切な検査や診察を受けることをお勧めします。
一番怖いのは、先ほどもお伝えしたように、症状が慢性化することです。
監修

倉敷インター接骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:岡山県倉敷市
趣味・特技:フットサル、絵を描くこと